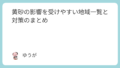認知症テストで出題される「絵を覚える問題」に不安を感じていませんか?
この記事では、実際に出題される絵のイラストパターンや、効率的に覚えるためのコツをわかりやすく解説しています。
A〜Dのイラストパターンや、語呂合わせ・ストーリーで覚える方法、そして本番で焦らないための準備や心構えまでしっかりフォロー。
「覚えられない…」と悩んでいる方も、この記事を読めば安心して認知症テストに臨めるようになりますよ。
ぜひ最後まで読んで、対策に役立ててくださいね!
認知症テストの絵を覚えるコツ7選
認知症テストの絵を覚えるコツ7選についてご紹介します。
- ①語呂合わせでイメージを強化する
- ②絵をストーリーとしてつなげて覚える
- ③ジャンル別にグルーピングする
- ④見た順に声に出して復唱する
- ⑤絵を自分の体験に結びつける
- ⑥1日1パターンずつ覚える
- ⑦思い出す練習を必ず行う
それでは、1つずつ詳しく説明していきますね。
①語呂合わせでイメージを強化する
まずおすすめしたいのが「語呂合わせ」です。
例えば、Aパターンの絵の中に「ライオン・ぶどう・ラジオ」があるとしたら、「ライオンがラジオを聴きながらぶどうを食べてる」みたいに、ちょっとおかしなシーンを想像してみてください。
意味が通じなくてもOK。むしろ少し変な方が、脳は「面白い!」って覚えやすくなるんです。
語呂合わせやユニークな組み合わせは、記憶の定着をグンと助けてくれますよ。
笑っちゃうようなストーリーが作れたら、完璧です!
②絵をストーリーとしてつなげて覚える
人間は「バラバラな情報」よりも「ストーリー」で覚えるのが得意なんですよね。
例えば、「オートバイ→ベッド→スカート→にわとり」という4つの絵が出るとします。
これを、「オートバイで旅行に出たら、ベッドの上にスカートがあって…にわとりが鳴いてた!」と、旅の物語風にアレンジするんです。
ストーリー仕立てにすると、記憶にスッと入ってきます。
映画やドラマのワンシーンを思い浮かべるように、想像力を膨らませてみてくださいね。
③ジャンル別にグルーピングする
16枚の絵をいきなり全部覚えるのは正直しんどいです…!
そこで、ジャンル分け(グルーピング)がおすすめ。
「動物」「道具」「植物」「乗り物」など、似たもの同士でまとめて覚えるんです。
グループで覚えることで、情報が整理されて、思い出すときにスムーズになりますよ。
たとえば「動物だけで覚えてみよう」など、1ジャンルずつ挑戦するのもアリです!
④見た順に声に出して復唱する
声に出すって、実は記憶にはかなり効果的なんです。
テストで絵を見たとき、「見た順番に名前を言ってみる」これだけでも記憶に残りやすくなります。
さらに、「聞く・話す・見る」を同時に使うことになるので、脳がフル活用されて、より記憶が定着しやすくなるんですよ~!
一人で練習するときも、恥ずかしがらずにどんどん声に出してみてくださいね。
スムーズに覚えられる実感、得られますよ!
⑤絵を自分の体験に結びつける
「これ昔見たことある!」って記憶って、なかなか忘れないですよね。
なので、絵を自分の体験や感情とつなげて覚えるのもおすすめです。
たとえば「フライパン」なら「母が作ってくれたオムライス」を思い出す、とか。
絵が感情とつながると、記憶の中に深く刻まれます。
自分の思い出を交えて覚えると、テスト中も思い出しやすくなるはずです!
⑥1日1パターンずつ覚える
一気に全部覚えようとすると、逆に覚えられなくなっちゃいます…。
なので、1日でAパターンだけ、次の日はBパターン…というふうに、少しずつ進めていきましょう。
4日間かけて4パターンを覚えるスケジュールにすると、焦らず落ち着いて覚えられます。
特に高齢の方にとっては、負担を減らすことも大切です。
無理せず、自分のペースで取り組んでくださいね。
⑦思い出す練習を必ず行う
最後に超大事なのが「思い出す練習」です!
人って「覚えたつもり」になって、いざという時に出てこないってこと…ありますよね。
なので、練習として「紙に書き出してみる」とか、「家族に口頭で話してみる」とか、アウトプットする時間を設けてください。
アウトプットすることで、記憶が長期に残りやすくなります。
“思い出す力”は、テスト本番で最も役立つ力なので、ぜひ試してみてくださいね。
イラストパターン一覧表 ABCDの別の絵のまとめ
イラストパターンABCDのパターン別!出題される絵の一覧まとめを紹介します。
それぞれのイラストパターンパターンにどんな絵があるのかを事前に知っておくと、心の準備ができて安心感につながりますよ。
①イラストパターンAパターンの16枚一覧
イラストパターンAに登場する絵は以下の16種類です。
| 大砲 | オルガン | 耳 | ラジオ |
| てんとう虫 | ライオン | たけのこ | フライパン |
| ものさし | オートバイ | ぶどう | スカート |
| にわとり | バラ | ペンチ | ベッド |
動物・植物・道具・乗り物など、ジャンルはバラバラですが、ストーリーにすると覚えやすくなります。
「オートバイに乗ってベッドの上でぶどうを食べるライオン」なんて想像すると、楽しく覚えられそうですよね!
②イラストパターンBパターンの16枚一覧
イラストパターンBで出題される絵は以下のとおりです。
| 戦車 | 太鼓 | 目 | ステレオ |
| トンボ | うさぎ | トマト | やかん |
| 万年筆 | 飛行機 | レモン | コート |
| ペンギン | 百合 | カナヅチ | 机 |
こちらもジャンルはさまざまで、音が出るものや動物も多いですね。
太鼓とステレオで音楽を聴きながら、ペンギンとうさぎがトマトとレモンのサラダを作ってる…そんなイメージで楽しく覚えてみてください♪
③イラストパターンCパターンの16枚一覧
イラストパターンCの内容は以下の通りです。
| 機関銃 | 琴 | 親指 | 電子レンジ |
| セミ | 牛 | トウモロコシ | ナベ |
| ハサミ | トラック | メロン | ドレス |
| クジャク | チューリップ | ドライバー | 椅子 |
クジャクやセミ、牛など自然系のものが多めです。
「親指を立てて、牛が琴をひく!」みたいな変なシチュエーションを思い描くのがコツです。
変なほど記憶に残りますから、遠慮せずにユニークなイメージを思い浮かべてみましょう!
④イラストパターンDの16枚一覧
イラストパターンDは次の絵が出てきます。
| 刀 | アコーディオン | 足 | テレビ |
| カブトムシ | 馬 | カボチャ | 包丁 |
| 筆 | ヘリコプター | パイナップル | ズボン |
| スズメ | ひまわり | ノコギリ | ソファー |
刀、包丁、ノコギリなど、ちょっと危ない道具も出てきますが、そこをうまく使ってストーリーを作ると逆に印象に残ります。
たとえば「馬がズボンをはいて、ヘリコプターでカボチャを運ぶ」みたいな物語がおすすめですよ!
認知症テストで合格するための注意点5つ
認知症テストで合格するための注意点5つをご紹介します。
本番で「えっ、こんなことで?」って焦らないように、事前にチェックしておきましょう。
①再テストになる基準を知っておく
まず知っておいてほしいのが、「どこまでミスしたら再テストになるか」という点です。
テストの点数は100点満点中36点以上が合格ラインです。
16枚の絵を何枚思い出せたかや、記憶の保持力が大きなポイントになります。
たとえば、絵を4つ以下しか思い出せなかったり、時間や季節の質問にうまく答えられないと、再検査になることがあります。
合格できなければ、免許更新に必要な講習を追加で受けないといけなくなるため、できるだけ一発合格を目指したいですよね。
②落ち着いて絵を見る時間を確保する
絵を見る時間は「何秒」って決まってるわけじゃありませんが、1枚ずつ見せられて、数秒のうちに頭に焼きつけないといけないんです。
ここで焦ってしまうと、見逃してしまったり、「どんな絵だったっけ?」と不安になることも。
なので、検査の直前は深呼吸して、心を落ち着けてから臨むようにしましょう。
見た瞬間に「何かと関連付けよう」とする姿勢も大事です。
“見る力”と“集中力”が、かなり試されるパートなので、心の準備が大切ですよ!
③焦らないでマイペースで答える
テスト中、「思い出せない!」と焦ってしまうと、さらに頭が真っ白になります…。
そんなときこそ、落ち着いて、ひとつずつ丁寧に思い出すことがポイント。
無理にすべて答えようとしなくても大丈夫です。
時間内で覚えていたものを、自分のペースで伝えましょう。
焦ると、それまで覚えていた内容も思い出しづらくなるので、「焦らないこと」は一番の防御策になります!
④聞かれた内容だけを答える
テストでは、「16枚の絵の中から覚えていたものを教えてください」と聞かれます。
ここで、記憶違いで“関係ない絵”を言ってしまう人が意外と多いんです。
テストはあくまで、「見せられた絵の中から」という制限があります。
だから、自分の記憶にある他のイラストや似た物を言わないように、注意してくださいね。
「出てきた絵だけ」を答える意識、これが高得点につながります。
⑤検査官の説明はしっかり聞く
最後にとても大切なのが、「検査官の説明をしっかり聞くこと」です!
緊張していたり、周りの音が気になってボーッとしていると、重要な指示を聞き逃してしまう可能性も。
検査の流れやルールは口頭で説明されることが多いので、聞き逃しがないように集中しましょう。
わからないことがあれば、遠慮なく質問して大丈夫です。
「聞く力」もテストの一部と考えて、しっかり受け止めてくださいね。
認知症テストを受ける前にやっておくべき準備
認知症テストを受ける前にやっておくべき準備についてご紹介します。
「やっておいてよかった」と思える準備をしておくと、当日安心してテストを受けられますよ!
①模擬テストをやってみる
いちばん効果的なのは、やっぱり事前に「模擬テスト」をやっておくことです!
絵を見て覚える→思い出して答える、という一連の流れを体験しておくと、本番で焦ることがグッと減ります。
ネット上でも、イラストパターンABCD各パターンの絵をまとめたサイトがありますので、実際にそれを見ながら練習するのがおすすめです。
とくに初めて受ける方は、「どんな雰囲気なのか?」をつかむ意味でも、模擬体験しておくと安心です。
「知ってる」だけでなく「やってみた」経験があると、落ち着いて取り組めますよ。
②目と耳の健康をチェック
認知症テストでは、「見る力」と「聞く力」も重要です。
小さな絵を瞬時に認識したり、検査官の声を正確に聞き取る必要があります。
そのため、事前に眼鏡や補聴器などの調整・点検をしておくと安心です。
テスト当日に「見えにくい」「聞こえづらい」というトラブルが起こると、それだけで不利になってしまいますからね。
目や耳の状態が不安な方は、かかりつけの医師に相談しておくのもアリです!
③十分な睡眠と水分補給
当たり前に見えて、実はとっても大切なのが「体調管理」です。
とくに睡眠不足の状態だと、記憶力や集中力が大きく落ちてしまいます。
前日は夜更かしせずに、しっかり眠っておくようにしましょう。
また、水分不足も集中力に悪影響を与えるので、テスト当日はコップ一杯の水を飲んでから出かけるのがおすすめですよ。
心と体がスッキリしているだけで、記憶力の働きがグンと変わってきます!
④家族や医師と相談しておく
不安を感じている方は、ぜひ家族やかかりつけ医と事前に話しておきましょう。
「こんな内容のテストを受ける予定なんだけど、大丈夫かな?」というだけでも、アドバイスやサポートを受けられることがあります。
とくに認知機能に不安がある方は、日常生活で困っていることなども伝えておくと、対策が立てやすくなります。
一人で抱え込まず、まわりの人と一緒に準備することが、安心につながります。
話すことで気持ちが軽くなることもありますから、ぜひ活用してみてくださいね。
認知症テストの絵が覚えられないときの対策
認知症テストの絵が覚えられないときの対策について解説していきます。
「どうしても覚えられない」と感じたときでも、まだできることはあります。
あきらめずに、できる対策をひとつずつ試していきましょう。
①無理に覚えようとしない
まず大事なのは、「無理に覚えようとしすぎないこと」です。
「絶対覚えなきゃ」と思うほど、プレッシャーで逆に記憶が入りにくくなります。
そんなときは、ちょっと視点を変えて「なんとなく思い出せそう」「ちょっと似てた」といったイメージレベルでOKだと思ってみましょう。
完全に覚えるのが難しくても、「見たときの印象」だけでも記憶に残っていることがあります。
気持ちに余裕を持って取り組むことが、結果的に記憶の定着を助けてくれますよ。
②人に説明するように思い出す
記憶って、自分の中で「思い出す」だけよりも、「誰かに説明する」つもりで思い出すほうが、ずっと覚えやすいんです。
例えば、家族や友人に「今日の練習で出た絵、何だったっけ?」と話してみる。
「フライパン、ライオン、オートバイだったかな…」みたいに口に出すと、自然と記憶が呼び起こされます。
声に出すことと、相手に伝える意識を持つことで、頭の中が整理されるんですね。
ひとりで黙々と覚えるのが苦手な方は、ぜひ試してみてください。
③イラストを繰り返し見る
「繰り返し」が記憶の基本です。
何回もイラストを見ることで、自然と「見慣れてきた」「あ、またこの絵だ」となる感覚がついてきます。
はじめは覚えられなくても、毎日1回ずつ4パターンを回すだけでも、かなり変わってきますよ。
無理に詰め込まず、1日5分でもいいので「毎日見る」ことを習慣化してみてください。
視覚に慣れるだけで、思い出す力がグッと上がってきます!
④間違えても気にしないメンタルを持つ
一番大事なのは、「間違えても落ち込まないメンタル」です!
誰でも間違えるし、完璧にできる人なんてそうそういません。
実際、テストでは全問正解じゃなくても合格ラインは超えられます。
だから、「1つや2つ思い出せなくても大丈夫」くらいの気持ちで臨んでくださいね。
失敗したときに「やっぱりダメだ…」って思ってしまうと、それが一番記憶に悪い影響を与えます。
「間違えるのは当たり前!次、またやってみよう」という姿勢が、何よりの対策になりますよ!
まとめ
認知症テストの絵をしっかり覚えるには、無理せず自分に合った方法を見つけることが大切です。
今回紹介した「語呂合わせ」「ストーリー化」「ジャンル分け」「声に出して復唱」などの7つのコツを使えば、記憶の定着がぐっと高まります。
特に「毎日少しずつ」「自分の体験と結びつける」といった工夫が、安心して本番に臨むための助けになります。
また、ABCD各パターンのイラスト内容を事前に確認することや、模擬テストで練習しておくことも効果的です。
不安を感じたら家族や医師と相談しながら、焦らず準備を進めましょう。
「思い出せない=ダメ」ではありません。日々の積み重ねと前向きな気持ちが、テスト成功への一番の近道ですだと思っています。