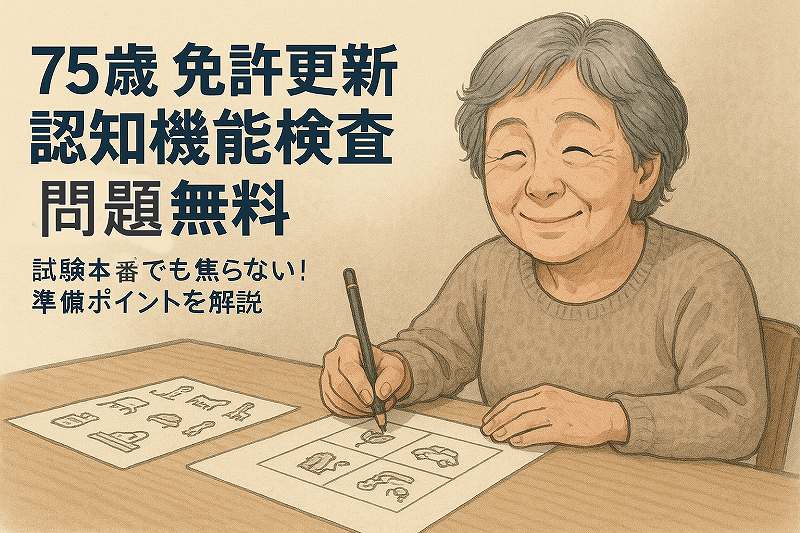75歳で運転免許を更新する際には「認知機能検査」が必要ですが、64枚のイラスト問題を無料で事前に対策すれば、安心して合格を目指せます。
この記事では、75歳以上の方が免許更新時に受ける認知機能検査の内容と、出題されるイラスト問題のパターン、効果的な覚え方、そして無料で使える練習問題の活用法をくわしく解説しています。
「どんな問題が出るのか分からない…」「覚えられるか不安…」そんな声に応える内容になっていますので、ご自身やご家族が検査を控えている方はぜひ参考にしてください。
合格のポイントと心構えが分かれば、75歳からでも自信を持って試験に臨めますよ。
75歳の免許更新に必要な認知機能検査とは
75歳の免許更新に必要な認知機能検査とは、どんな内容なのかをご紹介します。
それでは順番に見ていきましょう。
①検査の目的と対象年齢
認知機能検査は、75歳以上の方が運転免許を更新する際に必ず受けることになる検査です。
これは、高齢ドライバーによる交通事故を防止するための重要なステップで、認知症などの兆候がないかを早期に把握する目的があります。
対象者は、75歳の誕生日以降に免許の更新期限を迎える方です。
また、一定の違反歴がある方は、追加で高齢者講習も必要になる場合があります。
つまり、この検査を受けないと、免許の更新手続き自体が進められなくなってしまうんですね。
ちょっとプレッシャーを感じるかもしれませんが、しっかり準備すれば大丈夫ですよ!
②出題される問題の内容
認知機能検査では、大きく分けて「記憶力」と「時間の見当識」が問われます。
なかでもメインとなるのが、16枚のイラストを4分間見て覚え、時間をおいてから思い出して書き出すという問題です。
このイラストは全部で64枚の中からA~Dの4パターンの中のどれかのパターンが出題される形式になっています。
つまり、「あらかじめテストの絵を見ておけばかなり有利」ということですね。
ほかにも、「今日は何年・何月・何日・何曜日ですか?」といった時間に関する設問や、注意力を問う課題も含まれています。
試験時間は30分程度で終わりますが、集中力が問われるので、準備しておくと安心ですよ。
③合格ラインと不合格の影響
認知機能検査は、得点によって合否が判断されます。
2022年の法改正により、現在はシンプルに「36点以上で合格」「35点以下は不合格」という基準が導入されています。
| 得点 | 判定 | 対応 |
|---|---|---|
| 36点以上 | 合格(認知症の恐れなし) | 高齢者講習を受ければ免許更新可能 |
| 35点以下 | 不合格(認知症のおそれあり) | 医師による診断書の提出が必要 |
つまり、点数が36点に届いていれば、基本的には安心して免許更新ができるということです。
逆に、35点以下になってしまった場合は、認知症の有無を判断するために医師の診断が求められます。
ただし、不合格イコール即免許取消というわけではなく、医師の判断次第では更新が可能になるケースもありますよ。
大切なのは、焦らず事前に対策して、落ち着いて臨むことです。
④検査の申し込み方法と流れ
検査の流れは次の通りです。
- 更新期間前に警察(公安委員会)から「認知機能検査の案内」が届く
- 指定の教習所や試験場に電話で予約を入れる
- 検査当日、受検料を支払って受検
- その結果に基づき、高齢者講習の要否が決まる
予約が混みあうこともあるので、案内が届いたら早めに連絡するのがおすすめです。
また、受検の際は筆記用具や眼鏡などの持ち物も忘れずに準備しましょう。
焦らず、しっかりスケジュールを組んで対応すればOKですよ。
認知機能検査のイラスト問題64枚を徹底解説
認知機能検査のイラスト問題64枚を徹底解説していきます。
それでは順番に見ていきましょう。
①全64枚のイラストとは?
認知機能検査で出題されるのは、あらかじめ用意された「64枚のイラスト」から16枚を選んで提示される記憶問題です。
これは「記憶力」を測定する重要なパートで、検査の中でも合否に直結する部分になります。
最初にイラストを見て覚える時間が4分ほどあり、その後、数字を探す課題を挟んでから、思い出して紙に書き出す流れになります。
このイラストは、以下の4つのパターンに分類されています。
- パターンA
- パターンB
- パターンC
- パターンD
どのパターンも、動物・野菜・台所用品・乗り物などがバランスよく含まれていて、いずれのパターンが出ても公平になるようになっているんですね。
つまり、出題されるイラストを事前に知っておくことが、最大の対策になるというわけです。
「見たことある!」と感じられるだけでも、記憶の引き出しがかなり開きやすくなりますよ。
②パターンA〜Dの違いを知っておこう
各パターンには、それぞれ異なる16枚のイラストが割り当てられています。
例を挙げると、こんな感じです。
| パターン | 代表的なイラスト |
|---|---|
| A | 大砲・てんとう虫・ぶどう・ベッド・オートバイ |
| B | 戦車・トンボ・トマト・ペンギン・コート |
| C | 牛・ドレス・チューリップ・トラック・ナベ |
| D | 刀・テレビ・カブトムシ・ズボン・ソファー |
実際にはもう少し数がありますが、ここでは代表例だけを紹介しました。
どのイラストも、抽象的ではなく誰もが見たことのある「身近なモノ」が使われています。
だからこそ、「どのパターンが出ても安心できるように、すべてを見ておくこと」が何よりの対策になります。
出題されるパターンは完全にランダムですので、A〜Dすべてに目を通しておきましょうね。
③イラストを覚えるコツと工夫
イラスト問題を攻略するためのコツは、ずばり「ストーリー記憶法」を使うことです。
例えば、パターンAならこういった流れが作れます。
「朝、大砲の音で目が覚めて → ベッドから飛び起きた → 外を見たらてんとう虫が飛んでいて → オートバイで出かけて → ぶどうを買って帰った」
このように、絵の出題順番ではないが物語を作ることで、イメージとして記憶に残りやすくなります。
さらに、こんな工夫も効果的です。
- 声に出して名前を読み上げる
- 手を使ってイラストを何度も書く
- 身近な人とクイズ形式で出し合う
覚え方に「音」「動き」「会話」を取り入れると、記憶に残る確率がぐっと高まります。
苦手なモノだけをピックアップして集中的に覚えるのもアリですよ!
④どれが出るか分からない?対策の基本
さきほども触れましたが、出題されるイラストのパターンは完全にランダムです。
そのため、「1パターンだけ覚えておく」だけでは危険なんですね。
理想は、A〜Dすべてのパターンに目を通して、代表的なイラストをいくつかピックアップしておくこと。
無料の問題集を使えば、全64枚が一覧でチェックできますし、プリントしておけば何度も見返すことができます。
また、「絵のヒント」はA~Dまで全て共通なっているので、記憶に残りやすくなるんですよ。
ポイントは、「1日1パターン」を目安に、毎日少しずつやること。
焦らずコツコツ取り組めば、誰でもしっかり対策できますよ!
無料でできる認知機能検査の対策法5選
無料でできる認知機能検査の対策法5選をご紹介します。
それでは順番に見ていきましょう。
①スマホやパソコンでどこでも練習
認知機能検査のイラスト問題は、無料で公開されているサイトがいくつかあります。
こちらの記事をおすすめします>>>
そういったサイトでは、64枚のイラストをパターン別に見られるようになっていて、スマホやパソコンから簡単にアクセスできます。
電車の中や病院の待ち時間、ちょっとした空き時間に画面を開いて確認するだけでも、記憶の定着に効果がありますよ。
「机に座って勉強するのは苦手…」という方でも、日常生活のスキマ時間を活かして無理なく続けられます。
とくに高齢者の方には、操作が簡単なスマホがおすすめです。LINEやインターネットが使えるなら、対策ページもすぐ開けますからね。
②プリントアウトで繰り返し復習
スマホが苦手な方は、無料のイラストパターンや問題をプリントアウトして紙で練習する方法がおすすめです。
イラストパターンの一覧表はこちら>>>
イラストパターンのA~Dの絵のパターンです↓
印刷しておけば、いつでも手に取って見られるので、「今日はこのパターンだけ」「食後に10分だけ」など、自分のペースで練習ができます。
紙に直接書き込めるのもいいところで、記憶した内容を思い出しながら書くことで、より記憶に定着しやすくなります。
家のテーブルに置いておくだけでも、「ちょっと見てみようかな」と自然と手が伸びるんですよね。
モノとして“見える化”しておくことで、継続しやすくなりますよ。
③語呂合わせとストーリーで記憶に残す
64枚のイラストを全部覚えるのは正直しんどいですよね。
そんなときは、「語呂合わせ」や「ストーリー記憶法」を使ってみましょう。
たとえば、「ベッド → ラジオ → にわとり → オートバイ」なら、
「ベッドで寝てたら、ラジオから音がして、にわとりが鳴いて、オートバイで出かける朝」みたいな物語にすると覚えやすくなります。
語呂合わせも、「ブドウ・バラ・ベッド・ベンチ」→「ブバベベ」で「武場部屋」と語感でくっつけると忘れにくいです。
ちょっと笑っちゃうような語呂のほうが、案外覚えやすかったりしますからね(笑)
とにかく「イラストをただの“単語”にしないこと」がコツです。
④家族と一緒にクイズ形式で練習
ひとりでやるのが苦手な方は、ぜひご家族を巻き込んでみてください。
たとえば、お孫さんやお子さんに「この絵、何だった?」とクイズを出してもらうだけでも、かなり違います。
人に答えることで記憶が整理され、自分がどれくらい覚えているかも客観的に確認できます。
また、「一緒にやろう!」ということで会話のきっかけにもなりますし、モチベーションも上がりますよ。
検査のためだけでなく、家族とのコミュニケーションにもなって、一石二鳥です。
「クイズを出して」と頼むのが恥ずかしい場合は、「見てもらうだけでもいいよ」と言えばOK。
大切なのは“続けること”ですからね。
⑤ネットでダウンロードできる無料問題集を活用
最後に紹介したいのが、「無料問題集のダウンロード活用」です。
先ほどの「②プリントアウトで繰り返し復習」でのダウンロードした資料を活用してください。
検索すれば、認知機能検査に対応した64枚の全イラストをまとめたPDF資料が見つかります。
これをダウンロードしておけば、いつでもオフラインで練習ができますし、印刷もできて非常に便利です。
たとえば「64枚のイラストが見開きで一覧になっている資料」などもあるので、それを冷蔵庫に貼ったり、トイレに置いたりしておくと、いつでも目に入ります。
“目にする回数を増やす”というのは、記憶定着の王道なんですよね。
費用は一切かからずに、本格的な対策ができるのが大きなメリットです。
まさに、「やらなきゃ損!」な方法ですよ。
試験本番でも焦らないための準備ポイント
試験本番でも焦らないための準備ポイントについて解説していきます。
本番当日を安心して迎えるために、準備しておけることはたくさんありますよ。
①会場までのルートと時間を事前に確認
試験当日は、なるべくゆったりした気持ちで臨むのがポイントです。
そのためには、試験会場までのアクセスをしっかり事前に調べておくことが大切です。
教習所や警察署など、場所によっては少し分かりづらい場所にある場合もあります。
Googleマップなどを使って、前日に所要時間をシミュレーションしておきましょう。
可能であれば、実際に一度足を運んでみると安心感が違いますよ。
「時間に余裕がある」というだけで、心にも余裕が生まれて、試験にも集中しやすくなります。
②持ち物チェックで当日の不安を減らす
忘れ物があると、それだけで焦ってしまい、集中力が落ちてしまうことも。
試験当日に必要なものを、前日には準備しておきましょう。
| 持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 受検案内ハガキ | 予約情報や時間が記載されている |
| 運転免許証 | 本人確認として必須 |
| 筆記用具 | 鉛筆またはボールペン、 |
| 眼鏡や補聴器 | 日常的に使用している場合は必携 |
| 受検料 | 教習所での支払いに必要 |
これらをチェックリストにして、前日の夜に一度全部確認しておくと安心です。
「全部そろってる!」という状態で会場に向かえると、気持ちにも余裕が出ますよ〜!
③落ち着くための呼吸法と心構え
「本番が始まる直前が一番緊張する…」という方、多いんじゃないでしょうか?
そんなときにおすすめなのが「深呼吸」です。
鼻からゆっくり3秒かけて息を吸って、口から5〜6秒かけてスーッと吐き出す。
これを2〜3回くり返すだけで、体がリラックス状態に切り替わってくれます。
緊張すると頭が真っ白になったり、焦って答えが出てこなくなることもありますよね。
だからこそ、「まず呼吸を整える」という習慣をつけておくと、本番でも平常心が保ちやすくなりますよ。
「深呼吸はお守り」だと思ってくださいね。
④「全部覚えなきゃ」は逆効果
試験対策をしていると、「16枚全部を完璧に覚えなきゃ!」って思いがちですが、これ実はNG。
36点以上が合格ラインなので、全部正解じゃなくても全然OKなんです。
むしろ、「半分くらい思い出せたら大丈夫」と思っておくほうが、気持ちに余裕が出て、かえって本番で力を発揮しやすいです。
そして大事なのは、「思い出せない絵があっても、あわてない」こと。
「思い出せなかった絵に気を取られて、他のも思い出せなくなった…」というのはよくある話です。
1つミスしても引きずらない。「次!次!」と気持ちを切り替えるのが勝負の分かれ目です。
完璧を目指さず、安心して取り組めるようにしていきましょうね。
75歳からでも安心!記憶に残りやすい覚え方7選
75歳からでも安心!記憶に残りやすい覚え方を7つご紹介します。
- ①声に出して読むことで定着アップ
- ②五感を使ってイメージで覚える
- ③1日1パターンに絞って集中
- ④物語形式でストーリー記憶
- ⑤似た単語で連想する
- ⑥書いて手を動かして覚える
- ⑦人に説明してアウトプット
それでは、それぞれの覚え方を詳しく解説していきますね。
①声に出して読むことで定着アップ
記憶に残すうえで、ただ目で見るだけではもったいないんです。
「声に出す」という行動を加えると、脳は“自分で話した情報”として強く印象づけられるんですね。
たとえば、「ぶどう、ベッド、にわとり、ペンチ…」といったイラストを、ゆっくりはっきり声に出して読み上げてみてください。
自分の耳で聞くことでもう一度情報が脳に入って、定着しやすくなります。
特に寝る前や朝起きたあとなど、静かな時間に声を出すと集中もしやすいですよ。
②五感を使ってイメージで覚える
人間の記憶は、「イメージ」と結びつくとグッと強くなります。
イラストを見たとき、「その音」「匂い」「触った感触」など、五感を想像してみてください。
たとえば「フライパン」なら、「ジュウ〜」という音や、手に持ったときの重さ、焼けたときの匂いを想像します。
「にわとり」なら、「コケコッコー!」という鳴き声、朝日、毛のふわっとした感じなど。
こうやって五感を総動員すると、ただ見るだけよりもはるかに印象に残ります。
少し大げさに思い描いてみるくらいが、ちょうどいいですよ!
③1日1パターンに絞って集中
「64枚全部を一気に覚えよう!」と思うと、それだけで疲れちゃいますよね。
そこでおすすめなのが、1日1パターンだけに集中する方法です。
たとえば今日は「パターンAだけを見る」と決めて、その16枚を徹底的に見る・書く・声に出す。
次の日はパターンB、その次はC…と順番にこなしていくことで、無理なく全体を網羅できます。
1日たった10分でも、積み重ねればしっかり記憶に残ります。
「やれた」という小さな達成感もあるので、気持ちも前向きになりますよ!
④物語形式でストーリー記憶
イラストをバラバラの単語として覚えるのは大変ですが、物語にすれば一気に覚えやすくなります。
たとえばこんな感じです。
「ベッドで目を覚ましたら、ラジオから音楽が流れて、にわとりが庭でコケコッコー。朝ごはんにぶどうを食べて、オートバイに乗って出かけた…」
このように、日常の中にイラストを取り入れてストーリー化すると、頭の中に映像として浮かびやすくなるんですね。
あえてちょっと面白い話にしたり、変な展開にするのも記憶に残すコツです(笑)
ぜひ自分だけの「オリジナルストーリー」を作ってみてください!
⑤似た単語で連想する
イラスト同士を関連づけて覚える方法も、記憶の助けになります。
たとえば、「ベッド」と「スカート」だったら、「寝る前に着替えるもの」といった関連性を想像できますよね。
「ライオン」と「にわとり」はどちらも動物としてくくれますし、「バラ」と「チューリップ」なら「花の仲間」として分類できます。
また、「フライパン」と「ナベ」はどちらも料理道具、「テレビ」と「ラジオ」は“情報を得る家電”という共通点があります。
このように、ジャンルや機能などでグループにして覚えておくと、「あれと一緒だったやつ!」と連想で思い出しやすくなるんです。
一つひとつをバラバラに覚えるより、つながりを持たせることで記憶の引き出しが増えますよ。
⑥書いて手を動かして覚える
書くことは記憶の基本です。
目で見て、声に出して、さらに手で書く。これだけで記憶の定着率がグッと上がります。
ノートや裏紙で構いませんので、覚えたイラストを何も見ずに思い出して書いてみてください。
思い出せなかったイラストは、あとでもう一度確認して復習しましょう。
たとえ間違えても、それを直す作業こそが大事なんです。
手を動かすと、脳の“運動野”が活性化して、記憶が強化されると言われていますよ!
⑦人に説明してアウトプット
覚えたことを人に話す、というのもとても効果的な方法です。
「今日は大砲とかてんとう虫とか覚えたよ〜」と話してみるだけで、自分の頭の中が整理されます。
説明するときは、ストーリーにして話すとより効果的です。
たとえば、「朝起きたらテレビがついてて、カブトムシが映ってた」みたいに、会話のように話してみると記憶にも残りやすいです。
家族に話すのが恥ずかしいなら、ぬいぐるみ相手でもOK!声に出すことが大事です。
人に教えることで、自分の理解も深まりますからね。ぜひやってみてください!
まとめ|75歳 免許更新 認知機能検査 問題 無料を不安なく対策するには
| 対策のポイント | リンク |
|---|---|
| 検査の目的と内容を知る | ①検査の目的と対象年齢 |
| イラスト問題64枚を把握する | ①全64枚のイラストとは? |
| 無料の練習方法で対策する | ①スマホやパソコンでどこでも練習 |
| 本番に向けた心構えをする | ①会場までのルートと時間を事前に確認 |
| 覚え方の工夫で記憶を定着させる | ①声に出して読むことで定着アップ |
75歳での免許更新には「認知機能検査」が必須となりますが、あらかじめ無料の問題集でイラストを確認し、コツを押さえて練習すれば十分に対応可能です。
本記事では、出題形式やパターン別の違い、ストーリー法や語呂合わせといった具体的な覚え方など、初めての方でも取り組みやすい内容をまとめました。
また、スマホや印刷による無料練習法を活用すれば、日常の中で少しずつ準備できます。
焦らず、完璧を目指さず、「やれることから一つずつ」が大切です。
不安な方も、自分のペースで準備を始めていきましょう。