塔婆供養は、一般的に三十三回忌までが目安とされています。
ただし、宗派や地域の風習、家庭の事情によって違いがあり、必ずしも決まった正解があるわけではありません。
この記事では、「何回忌まで塔婆が必要なのか?」という疑問に対して、宗派別の考え方、省略できるケース、費用の目安までわかりやすく解説しています。
初めて法事を任された方や、準備に悩んでいる方にとって、安心して判断できるヒントが見つかるはずです。
ぜひ最後まで読んで、あなたのご家庭に合った供養の形を見つけてくださいね。
塔婆供養は何回忌まで必要なのか徹底解説

塔婆供養は何回忌まで必要なのか徹底解説していきます。
それでは詳しくみていきましょう。
①一般的な目安は三十三回忌まで
塔婆供養が必要なのは「三十三回忌」までが一般的な目安とされています。
特に一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・十七回忌・二十三回忌・二十七回忌・三十三回忌などの節目で、塔婆を立てるのが慣習となっています。
ただ、近年では三十三回忌をもって「弔い上げ」として供養の一区切りとする家庭も多く、それ以降の供養は行わないというケースもあります。
このあたりは、家族やお寺との相談で柔軟に決めてOKです。
とはいえ、「三十三回忌までは供養を続けよう」という考えが今でも根強く残っていますので、参考にしてくださいね。
ちなみに筆者の実家では、祖父の三十三回忌を区切りに塔婆供養を終えました。
②宗派によって異なる慣習
塔婆供養は宗派によっても大きく考え方が異なります。
たとえば、日蓮宗では塔婆を非常に重要視しており、回忌法要では必ず塔婆を立てるべきとされています。
一方で、浄土真宗では基本的に塔婆を立てるという文化がありません。
これは、塔婆自体が「供養の一環」とされる宗派と、「念仏を唱えることこそ供養」とされる宗派との違いからくるものです。
なので、自分の家の宗派をまず確認することが大切ですよ。
お寺に相談すれば、その宗派での適切な供養のあり方を教えてもらえます。
③地域による風習の違いもある
宗派だけでなく、地域によっても塔婆供養の風習はさまざまです。
都市部では簡略化が進んでいて、「塔婆を立てるのは一周忌と三回忌だけ」というケースも増えてきています。
一方で、地方では今でも丁寧な法要が行われていて、節目ごとにきちんと塔婆を用意することが当たり前という地域もあります。
親戚やご近所との関係性を考慮して、地域の風習にも配慮した判断をすると安心ですね。
地元のお寺に確認するのが一番確実な方法ですよ。
④塔婆を立てる意味と供養の本質
そもそも塔婆ってなに?と思っている方も多いですよね。
塔婆は「卒塔婆(そとば)」といって、サンスクリット語の「ストゥーパ(仏塔)」が語源です。
もともとは釈迦の遺骨を納めた仏塔を模したもので、そこにお経や戒名を書くことで、故人の供養になるとされています。
つまり、塔婆は単なる儀式的なものではなく、「心を込めた供養のカタチ」なんです。
塔婆を立てることで、遺族の「忘れてないよ」という思いを形にすることができますよ。
費用や手間の問題もありますが、その本質を理解したうえで行動できるといいですね。
塔婆供養を省略してもいいケースと判断基準
塔婆供養を省略してもいいケースと判断基準について解説します。
状況に応じて柔軟に判断していきましょうね。
①身内だけの法要で簡素化する場合
近年では「家族葬」や「身内だけの法要」が増えてきていますよね。
このような場合、あえて塔婆を立てずに、簡素な形で供養を行うこともよくあります。
塔婆はあくまで供養の一つの方法なので、家族内で合意が取れていれば、形式にこだわらずとも問題ありません。
例えば、自宅でお経をあげてもらうだけのシンプルな一周忌などでは、塔婆を省略しても失礼にはあたりません。
大切なのは「気持ちのこもった供養」であって、必ずしも形にする必要はないという考え方も広がっています。
筆者の知人の家庭では、高齢の両親だけでの法要だったため、塔婆なしで静かに供養されたそうですよ。
②お寺との相談で不要と判断された場合
塔婆を立てるかどうか迷ったときは、まずお寺に相談するのが一番です。
宗派やそのお寺の考え方によって、「今回は立てなくても大丈夫ですよ」と言ってくれることもあります。
特に浄土真宗など塔婆供養の習慣がない宗派では、塔婆自体が不要とされています。
また、少人数でのお参りや納骨堂での法要など、スペースや時間の制限から塔婆を立てづらいケースもあるんです。
そんなときは、お寺側が柔軟に対応してくれることが多いので、遠慮せずに相談してみてくださいね。
③経済的・物理的に難しいとき
現実的な問題として、塔婆供養には費用がかかります。
相場としては1本3,000円~10,000円程度。複数本になると、かなりの負担になることも。
| 塔婆の本数 | 平均費用 |
|---|---|
| 1本 | 3,000~10,000円 |
| 3本 | 9,000~30,000円 |
| 5本 | 15,000~50,000円 |
経済的に厳しいときは、無理に塔婆を用意する必要はありません。
また、高齢者や遠方在住の方にとっては、塔婆を依頼したり運んだりすること自体が負担になることもありますよね。
その場合は「心で手を合わせる」ことを優先して、自分たちなりの供養をすれば大丈夫ですよ。
④故人の遺志がある場合
故人が「質素にやってくれればいい」と言っていた場合や、「供養は心だけで十分」と考えていた場合、塔婆供養を省略することに迷う必要はありません。
最近では終活の一環で「葬儀や法要はなるべくシンプルにしてほしい」と伝える方も多くなっています。
そんなときは遺志を尊重して、塔婆なしの法要を行ってもまったく問題ありません。
むしろ、故人の考えを大切にするという意味では、とても意味のある供養になりますよ。
迷ったときは、遺されたメモや家族での会話を思い出してみてくださいね。
「気持ちが伝わること」が、何よりも大切だと思います。
宗派別の塔婆供養の違いを知っておこう
宗派別の塔婆供養の違いを知っておこう。
塔婆供養の考え方は、実は宗派によってかなり違うんです。
①浄土宗・浄土真宗の考え方
まずは、よく耳にする「浄土宗」と「浄土真宗」から見ていきましょう。
浄土宗では、塔婆供養は一般的に行われていますが、それほど重視されていないという特徴があります。
一方、浄土真宗になると話はガラリと変わります。
浄土真宗では「阿弥陀仏の本願にすがり、念仏を称えること」が最大の供養とされるため、塔婆そのものを立てないのが基本なんです。
なので、「うちは塔婆立てなきゃダメかな?」と不安な方でも、もし浄土真宗であれば、そもそも立てない方が自然なケースもあります。
筆者も、知人の家が浄土真宗で、一切塔婆供養を行わないことに最初驚きましたが、話を聞くと理にかなっていて納得でした。
②曹洞宗・臨済宗の塔婆の有無
続いて、禅宗系の「曹洞宗」や「臨済宗」の場合です。
この2つの宗派では、基本的には塔婆を立てる風習があります。
特に、墓前供養や年忌法要の際には、塔婆を立てて読経を行うのが一般的ですね。
ただし、禅宗は「質素を良しとする」傾向が強いため、形式にこだわらず、塔婆も必要最低限にとどめるという考えも根付いています。
法事の参加人数が少ない場合など、塔婆の本数も調整されることがありますよ。
臨済宗では、塔婆に梵字や仏教的な文言を記すことで功徳を得るとされていて、意味合いも深いです。
地域やお寺の方針にもよりますが、基本的には塔婆供養が存在する宗派です。
③日蓮宗における塔婆の重要性
日蓮宗といえば、塔婆供養を非常に重視する宗派として知られています。
日蓮宗では、法華経の教えに基づき、塔婆を立てて供養することが大きな功徳をもたらすとされています。
塔婆には「題目(南無妙法蓮華経)」が書かれ、これ自体が仏の教えそのものとされているんですね。
そのため、年忌法要はもちろん、お盆や命日などの節目でも塔婆を立てるのが一般的です。
お寺によっては、事前に必要な本数を申し出ておかないと間に合わないということもあるので、計画的に動く必要があります。
このように、塔婆供養が「絶対に必要」とされる宗派の代表が日蓮宗なんです。
④真言宗の特徴と供養スタイル
最後に、真言宗についてご紹介しますね。
真言宗は密教に属する宗派で、儀式や供養にとても力を入れる傾向があります。
塔婆供養についても、非常に丁寧に行うことが多く、卒塔婆には「梵字」「戒名」「経文」などが書かれます。
特に十三回忌以降も供養を大切にする傾向があり、三十三回忌までしっかり続けるご家庭が多いですね。
また、真言宗では供養そのものが「故人の成仏」を願う修行の一環とされるため、塔婆の意味合いも深いです。
家族で供養に参加する意識も高く、お経と合わせて塔婆供養を行うことで、心の安らぎを得られるとされています。
供養を通じて、自分たちの心も整えるというのが真言宗らしいところですね。
塔婆供養の費用相場と頼み方のコツ
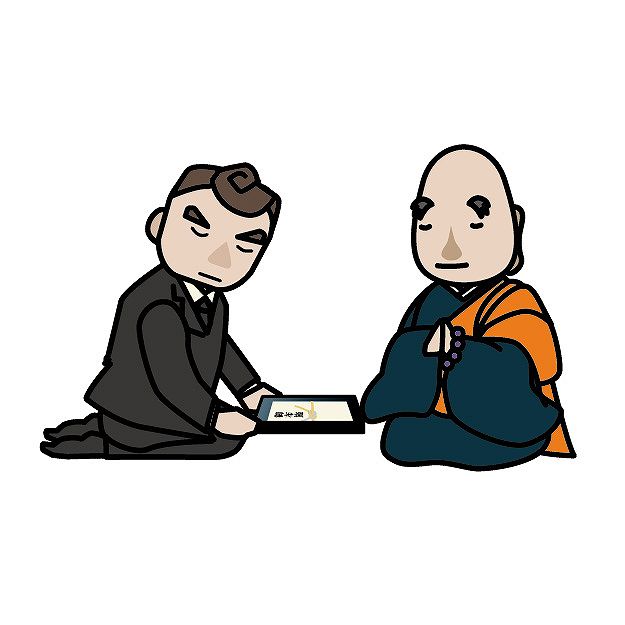
塔婆供養の費用相場と頼み方のコツについて詳しく解説していきます。
費用感や依頼の流れが分かれば、準備もスムーズにできますよ。
①1本あたりの費用と内訳
まずは、塔婆1本あたりにかかる費用の相場からお話しますね。
一般的には、1本3,000円〜10,000円程度が相場です。
費用に幅があるのは、お寺ごとに設定が違うからなんです。
この金額には、塔婆そのものの材料費だけでなく、お経をあげてもらうための準備費用や、書き込みに使われる墨や筆の費用、そしてお坊さんの時間などが含まれています。
特に日蓮宗や真言宗など、文字数が多く複雑な塔婆になると、書き上げにも時間がかかるため、その分費用が高くなることもありますよ。
事前に「費用はどれくらいですか?」とお寺に聞くのは全然失礼じゃないので、遠慮せずに確認しておきましょう。
②複数本立てる場合の注意点
法要で「家族全員分の塔婆を立てたい」となると、費用がけっこうかさみます。
例えば5本頼んだ場合、1本3,000円でも15,000円、1本10,000円ならなんと5万円に達することも。
さらに、塔婆を立てるスペースにも限りがありますので、墓地のサイズも要チェックです。
供養したい親族が多いときは、代表者の名前で1本立てるだけにして、あとは気持ちだけお供えする方法もあります。
実際、筆者の親族の法要では、「祖父母連名で1本だけ塔婆を立てる」という形にして、負担を減らしていました。
故人や家族の気持ちを第一に考えて、無理のない方法を選ぶのがポイントですよ。
③お布施との関係性
塔婆供養の費用と混同されがちなのが「お布施」です。
お布施は「お坊さんにお経をあげていただいたことへの感謝の気持ち」なので、塔婆の費用とは別になります。
例えば、塔婆が1本5,000円、法要でのお布施が20,000円という形で、それぞれ個別に包むのが基本です。
ただし、地域やお寺によっては「塔婆代込みのお布施」としてまとめて包むケースもあるので、事前に確認が必要です。
迷ったときは、「塔婆代とお布施は分けた方がいいですか?」とストレートに聞いてしまって大丈夫ですよ。
封筒には、表書きとして「御塔婆料」「御布施」と書いて、中袋には金額と住所・名前を明記するのがマナーです。
④お寺への依頼方法とマナー
塔婆を依頼する際には、いくつかのマナーがあります。
まず、法要の予定が決まったら、できるだけ早めにお寺へ連絡しましょう。
塔婆には「戒名」や「命日」などの正確な情報が必要になるため、間違いのないように控えておくことが大切です。
依頼する本数や、誰の分をお願いするのかも明確に伝えてくださいね。
当日は、塔婆代を「御塔婆料」として封筒に入れて持参し、受付や住職にお渡しします。
そして、できれば感謝の気持ちを一言添えてください。
「お世話になります」「よろしくお願いします」といった言葉だけでも、丁寧な印象になりますよ。
丁寧なやりとりが、お寺との関係を良好に保つコツです。
塔婆供養を続けることの意味と家族の絆
塔婆供養を続けることの意味と家族の絆について考えてみましょう。
塔婆供養を「ただの儀式」と思わずに、その背景や意味を大切にしたいですね。
①供養は気持ちを形にするもの
塔婆供養は、いわば「心を目に見える形にしたもの」です。
供養の気持ちを表す方法はいろいろありますが、その中でも塔婆は最も「具体的」な形と言えるかもしれません。
戒名や経文を記した木の札に、遺族の想いや祈りが込められているんですよね。
忙しい日々のなかでも、「今日はおじいちゃんの三回忌だから塔婆をお願いしよう」と思うその行為こそが、供養の本質です。
形にすることで、自然と気持ちも整うし、故人を思い出す時間ができるんですよね。
②故人との心のつながりを保つ
人は亡くなっても、思い出や教えはずっと生き続けます。
塔婆を立てるという行為は、そんな「見えないつながり」を大切にすることにもなります。
法要の日に家族が集まり、塔婆の前で手を合わせる。
その瞬間、たとえ姿は見えなくても、故人がそこにいるような感覚になりますよね。
それは、心のなかで「今でも大切に思ってるよ」というメッセージを送り続けているということなんです。
供養は亡き人のためだけじゃなく、自分たちの心の整理のためでもあるんだなぁと思います。
③子や孫への教育としての価値
最近では、法事や供養の文化が薄れてきているとも言われています。
でも、子どもたちに「人を思いやること」「感謝を形にすること」を伝える機会として、塔婆供養はとても意味があります。
たとえば、孫が「この塔婆は誰の?」と聞いてきたときに、「これはおばあちゃんのだよ」と教えてあげる。
そこから家族の歴史を話すきっかけになったり、「命のつながり」を感じる場面にもなりますよね。
供養を通じて、思いやりの心や日本文化を自然と学ぶことができる…それって本当に素敵なことです。
④家族の結束を深めるきっかけになる
法要や供養って、親族が集まる貴重な時間でもあります。
忙しくてなかなか会えない親戚とも、塔婆を立てる法事のタイミングで再会できたりしますよね。
「久しぶり〜!」なんて会話を交わしながら、お墓の前で手を合わせると、なんだか家族の一体感を感じたりもします。
それが塔婆という「共通の目的」があるからこそ、自然と生まれるつながりなんです。
形式的なことに思えるかもしれませんが、その裏には家族の絆を深める大きな力があるんですよ。
筆者自身も、祖父の七回忌で久々に従兄弟と再会して、子ども時代の話に花が咲きました。供養の場がなかったら、それもなかったなぁと思います。
まとめ|塔婆は何回忌まで必要なのか、正しく理解しよう
| 塔婆供養は何回忌まで必要なのか徹底解説 |
|---|
| ①一般的な目安は三十三回忌まで |
| ②宗派によって異なる慣習 |
| ③地域による風習の違いもある |
| ④塔婆を立てる意味と供養の本質 |
塔婆供養は「三十三回忌まで」が一つの目安ですが、宗派や地域、家庭の事情によっても変わってきます。
特に、浄土真宗のように塔婆供養を行わない宗派もあれば、日蓮宗のように重要視する宗派もあります。
また、近年では家族葬や小規模な法要が増えてきており、省略するケースも珍しくありません。
それでも、塔婆供養には「心を形にする」「故人とのつながりを保つ」といった大切な意味があります。
迷ったときは、お寺や家族とよく相談して、自分たちらしい供養の形を見つけてくださいね。
供養を通して、家族の絆や、いのちのつながりを見つめ直すきっかけになれば幸いです。
さらに詳しい供養の考え方や法事の手順については、以下の資料もぜひご参照ください。


